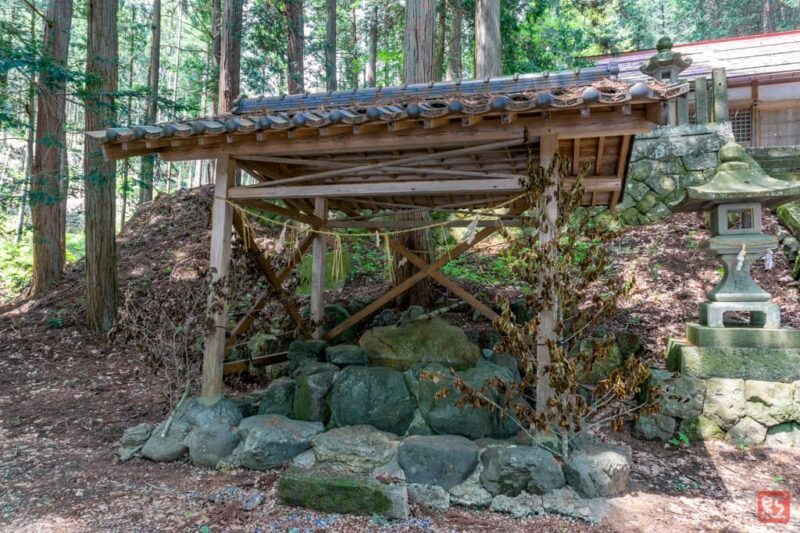四天王神社。
高山市漆垣内町に鎮座。
日本三代実録 貞観9年(867)10月5日庚午条に見える四天王神に比定される神社。
境内
社頭
社号標
鳥居
手水舎
狛犬
社叢?の木々の中に巨岩
何らかの由緒ある岩なんでしょうか。
社殿
拝殿
本殿
由緒
創建時期は不詳。
三代実録 貞観9年(867)10月5日庚午条に見える「飛騨国正六位上…四天王神…並従五位下」の四天王神は当社に比定されています。
『飛騨の神社』『岐阜縣神社名鑑』によると、仏法護持の四天王神を祀ったとの説より、四天王神社と称するようになったとされます。現祭神は異なりますが、『斐太後風土記』では祭神を護世四天王神(多聞天・持国天・増長天・広目天)としています。
金森長近は当社への一般民衆の参拝を禁止せず、遥拝所を二之宮(漆垣内町の二之宮神社か)、当社天王宮を奥宮としたと伝えられます。
中世から近代は天王宮と称していたようで、明治4年に四天王神社に改称(復称)。
かつては境内に古墳二基があったようです(明治末期に破壊され現存せず)。
『飛騨の神社』によると、当社の鎮座する漆垣内の地名は「大和時代の末、物部氏と藤原氏争乱の折、聖徳太子が四大王像をみずらに飾って戦われたことから、四天王像を刻んだ「白膠の木」、すなわち「漆の木」より」生まれたという説があるとのこと。
ただこのエピソード、丁未の乱でのものだと思われるので、藤原氏は蘇我氏の誤りかと思われます。河内国での戦いの際の話がなぜ飛騨の地名に繋がるのかは不明。
現祭神は須佐之男命。
中世~近代に天王宮とされていた頃に牛頭天王が祀られ、後に須佐之男命になったと思われます。
上述の通り仏法護持の四天王神が元々の祭神だとすると、いつ頃天王宮となったのでしょうか。
配祀神が八柱祀られていますが、日光の神、月光の神はどういった神なのでしょう(天照大御神、月読命とは違うのでしょうか…)。
御朱印
御朱印の有無は不明。
アクセス
高山市中心部から国道158号を東へ。松之木町東交差点(位置、ファミマのあるところ)を右折。
1.5kmほど先(位置、二之宮神社のちょっと西の十字路)で左折。
300mほど先で左折(位置、自販機があるところ、わかりづらい)。
そのまま直進で神社。最後の左折から神社までは道狭いので注意。
駐車場はありません。が、境内に乗り入れは可能。
神社概要
| 社名 | 四天王神社(してんのうじんじゃ) | |
|---|---|---|
| 通称 | – | |
| 旧称 | 天王宮 | |
| 住所 | 岐阜県高山市漆垣内町505-2 | |
| 祭神 | 須佐之男命 | 現祭神 |
護世四天王神 (多聞天・持国天・増長天・広目天) | 『斐太後風土記』 | |
| 配祀 | 櫛稲田姫命 斎火武主比命 天照国照彦火明命 奥津比古命 大八椅命 奥津比売神 日光の神 月光の神 | |
| 社格等 | 日本三代実録 貞観九年十月五日庚午 四天王神 従五位下 旧村社 | |
| 札所等 | – | |
| 御朱印 | 不明 | |
| 御朱印帳 | – | |
| 駐車場 | なし | |
| 公式Webサイト | – | |
| 備考 | – | |
参考文献
- 「四天王神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995
- 岐阜県神社庁編『岐阜縣神社名鑑』岐阜県神社庁, 2017
- 土田吉左衛門編『飛騨の神社』飛騨神職会, 1988
- 富田礼彦『斐太後風土記 上』(大日本地誌大系第七冊)大日本地誌大系刊行会, 1915(国会図書館デジタルコレクション 63コマ)